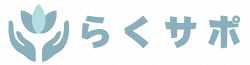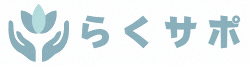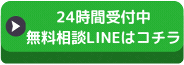仏壇じまいの費用と正しい手順
後悔しない進め方がこれ1つで分かる
【2026年3月更新】
「仏壇をしまうにはどうしたらいい?手順や費用が分からない…」
「仏壇じまいって、罰当たりじゃないの? ご先祖様に申し訳ない気がして…」
もしあなたが今、こんな不安を抱えているなら、この記事はきっとお役に立てます。
親の施設入居や実家の整理をきっかけに、仏壇じまいを考える50〜60代の方が急増しています。
しかし、いざ進めようとすると、「正しい手順がわからない」「費用がどれくらいかかるか不安」と、多くの疑問や不安が出てくるのではないでしょうか。
実は、仏壇じまいは「罰当たり」ではありません。
正しい手順で仏壇や位牌を整理・処分すれば、ご先祖様に対しても、家族に対しても、誠実な供養となります。
むしろ、時代の変化に伴い、「無理なく供養を続けられる形に変える」ことこそが、現代における正しい供養の在り方と言えるでしょう。
この記事では、
- 仏壇じまいの正しい流れ
- 宗派ごとの違いと注意点
- お布施や処分にかかる費用の目安
を、初めての方にもわかりやすく解説します。
読み終わる頃には、仏壇じまいの手順が明確になり、家族や親族との話し合いや金額などを押さえた上で、安心して仏壇じまいを進められる状態になります。
ぜひ最後までお読みください!
処分にお困りの
仏壇お引取りします
搬出から積込みまで全て対応
お仏壇の供養も対応
お仏壇の処分8,000円から
年中無休・24時間受付中
タップしてお電話ください
目次
仏壇じまいは「罰当たり」ではない・正しい供養を知ろう
「仏壇を処分するなんて、ご先祖様に申し訳ない…」
「罰が当たるんじゃないか…」
仏壇じまいを考え始めた時、多くの方がこうした不安を感じます。
しかし、仏壇じまいは決して「罰当たり」な行為ではありません。
仏壇じまいは時代に合わせた「供養の形の変化」です。
仏壇は、ご先祖様を供養するための大切な場所です。
しかし、昔と今では、私たちの生活環境が変わった中で、「無理なく供養を続けられる形に変える」ことは、むしろご先祖様への誠実な姿勢と言えます。
「魂抜き供養」を行えば、宗教的にも問題ない
仏壇には、購入時に僧侶による「魂入れ(開眼供養)」が行われています。
これは、仏壇に仏様やご先祖様の魂を宿らせる儀式です。
仏壇じまいをする際は、この逆の儀式である「魂抜き(閉眼供養)」を行います。
魂抜きを行うことで、仏壇は「魂の宿る神聖なもの」から「ただの家具」に戻ります。
その後、仏壇を処分しても、宗教的に何の問題もありません。
用語解説
魂抜き(たましいぬき)
仏壇や位牌から魂を抜く儀式。「閉眼供養(へいがんくよう)」「性根抜き(しょうねぬき)」とも呼ばれます。宗派によって呼び方が異なりますが、意味は同じです。
50代以上の約4割が仏壇じまいを検討している
実は、仏壇じまいを検討している方は年々増えています。
ある調査によると、50代以上の約4割が「将来的に仏壇じまいを考えている」と回答しています。
つまり、あなただけが特別なのではなく、多くの人が同じ悩みを抱えているのです。
「自分だけが親不孝なのでは…」と思う必要はありません。
時代の変化に合わせて、ご先祖様への感謝の気持ちを持ちながら、現実的な判断をすることは、決して間違っていません。
【重要】まず確認!宗派による仏壇じまいの違い
仏壇じまいを進める前に、必ず確認すべきことが一つあります。
それは、「自分の家の宗派」です。
なぜなら、宗派によって「魂抜き」の考え方や呼び方が異なるからです。
宗派別の魂抜きの必要性
| 宗派 | 魂抜きの呼び方 | 必要性 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 浄土真宗 | 遷座法要(せんざほうよう) | △ | 「魂」という概念がないため、厳密には魂抜きは不要。 |
| 曹洞宗・臨済宗 | 閉眼供養(へいがんくよう) | ○ | 必要。菩提寺(ぼだいじ:先祖代々お世話になっているお寺)に依頼します。 |
| 真言宗・天台宗 | 性根抜き(しょうねぬき) | ○ | 必要。菩提寺に依頼します。 |
| 浄土宗 | 閉眼供養 | ○ | 必要。菩提寺に依頼します。 |
| 日蓮宗 | 魂抜き | ○ | 必要。菩提寺に依頼します。 |
「自分の家の宗派がわからない」場合の確認方法
「そもそも、うちの宗派って何だろう?」
そんな方は以下の方法で確認できます。
方法1:仏壇の中の本尊(仏像)で判別する
仏壇の中央には、必ず「本尊(ほんぞん)」と呼ばれる仏像や掛け軸があります。
この本尊を見れば、宗派がわかります。
| 本尊 | 宗派 |
|---|---|
| 阿弥陀如来(あみだにょらい) | 浄土宗・浄土真宗 |
| 釈迦如来(しゃかにょらい) | 曹洞宗・臨済宗 |
| 大日如来(だいにちにょらい) | 真言宗 |
| 南無妙法蓮華経の掛け軸 | 日蓮宗 |
方法2:過去の法事の案内状を確認する
過去に法事(四十九日、一周忌など)を行った際の案内状や、お寺からの手紙が残っていれば、そこに宗派が書かれていることがあります。
方法3:親戚に聞く
叔父・叔母など、年配の親戚に聞くのが最も確実です。
「うちの宗派って何だったか覚えてる?」と気軽に聞いてみましょう。
方法4:お寺に直接問い合わせる
お寺(先祖代々お世話になっているお寺)がわかっている場合は、直接電話で聞くのが確実です。
「○○家の〇〇と申しますが、うちの宗派を確認させていただけますか?」と聞けば、丁寧に教えてくれます。
浄土真宗の方への注意点
もしあなたの家が浄土真宗の場合、少し特殊です。
浄土真宗では、「魂」という概念がありません。
そのため、厳密には「魂抜き」は不要です。
ただし、仏壇を購入した時に行った「入仏法要(にゅうぶつほうよう)」の解除として、「遷座法要(せんざほうよう)」を行うこともあります。
お寺に「仏壇じまいをしたい」と相談すれば、適切な方法を教えてくれます。
仏壇じまいの流れ|4ステップでわかる進め方
それでは、仏壇じまいの具体的な流れを見ていきましょう。
全体の流れは、以下の5つのステップです。
仏壇じまい4ステップ
- 家族・親戚へ相談して了承を得る
- お寺に連絡して、魂抜き(閉眼供養)を依頼する
- 仏壇の中身を整理する(位牌・仏具・掛け軸)
- 仏壇を処分する(お寺・仏具店・業者)
それぞれ詳しく見ていきましょう。
ステップ1:【最優先】家族・親戚へ相談して了承を得る
仏壇じまいで最も重要なのは、「家族・親戚への相談と合意」です。
「まずはお寺に連絡しなきゃ」と思うかもしれませんが、その前に必ず家族に相談しましょう。
なぜ最初に相談が必要なのか
仏壇は、あなた一人のものではありません。
家族全員の供養の場であり、特に母や兄弟姉妹にとっても大切な存在です。
独断で進めてしまうと、
- 「なぜ相談してくれなかったの?」
- 「勝手に処分するなんて信じられない」
- 「ご先祖様に申し訳ない」
と、家族や親戚から非難される可能性があります。
後々のトラブルを避けるためにも、事前の相談と合意は必須です。
誰に相談すべきか(優先順位)
相談すべき相手を、優先順位順に並べると以下のようになります。
- 父母(仏壇を守ってきた本人)
- 兄弟姉妹
- 叔父・叔母など近い親戚
- お寺(宗教的な確認)
特に、父母の気持ちを最優先にしましょう。
長年仏壇を守ってきた両親にとって、仏壇じまいは大きな決断です。
「仏壇を継ぐ人がいないから仕方ない」と一方的に進めるのではなく、両親の気持ちに寄り添いながら、一緒に最善の方法を考えることが大切です。
話し方は以下を参考にしてみてください。
【例文】母への相談の仕方
「お母さん、老人ホームに入居することになって、実家の仏壇をどうするか考えないといけないんだけど…。
大きな仏壇は老人ホームに持っていけないし、私たちの家も狭くて置けないの。
でも、ご先祖様を粗末にするつもりは全くなくて、きちんとお寺で魂抜き供養をしてもらって、小さな手元供養に切り替えようと思ってるの。
そうすれば、老人ホームでも毎日手を合わせられるし、私も定期的にお参りできるから。
お母さんはどう思う?」
ポイント:手元供養を提案してみよう
親に「仏壇を処分する」とだけ伝えると、抵抗感が強くなります。
そこで、「小さな手元供養に切り替える」という代替案を提示しましょう。
手元供養とは、小さな仏壇や位牌を使って、身近な場所で供養を続ける方法です。
「供養をやめるわけではない」「これからも毎日手を合わせられる」と伝えることで、両親も納得しやすくなります。
ステップ2:お寺に連絡して、魂抜き(閉眼供養)を依頼する
家族・親戚の了承が得られたら、次はお付き合いのある寺への連絡です。
お付き合いのある寺への連絡方法
お寺への連絡は、電話が基本です。
メールやLINEは避けましょう。
仏事は対面や電話でのやり取りが礼儀とされています。
連絡するタイミング
お寺に電話をかける際は、以下のタイミングを避けましょう。
- 午前中の早い時間(9時前):お寺の朝のお勤めの時間
- お昼時(12時〜13時):昼食の時間
- 夕方の遅い時間(17時以降):夕方のお勤めの時間
おすすめの時間帯は、10時〜11時、または14時〜16時です。
【例文】僧侶への相談の仕方
「お世話になっております。○○家の〇〇と申します。
実は、母が老人ホームに入居することになりまして、実家の仏壇をどうするか考えております。
仏壇じまいをする場合、閉眼供養をお願いしたいのですが、可能でしょうか?
また、その際のお布施の目安や、位牌の供養についても教えていただけますでしょうか?」
お寺に確認すべきこと
電話で以下の点を確認しましょう。
- 閉眼供養の日程
- 希望日の2〜3週間前に連絡するのが理想
- 法事が多い時期(お盆、お彼岸)は避ける
- お布施の目安
- 「お気持ちで」と言われることが多いが、「皆様どれくらい包まれていますか?」と聞けば教えてくれる
- 相場は1万円〜5万円(地域や寺院との関係性による)
- 供養の場所
- 位牌をお寺で処分してもらえるか
- 仏具(線香立てやリンなど)の処分方法
魂抜き供養当日の流れ
当日の流れ
魂抜き供養の当日は、以下のような流れになります。
所要時間:30分〜1時間
- 読経・閉眼供養の儀式
- 法話(お坊さんによるお話)
- お布施を渡す
参列者:家族・親戚(希望者のみ)
服装:平服でOK(喪服は不要)
お布施の渡し方:
- 白い封筒に入れる
- 表書きは「御布施」または「閉眼供養御礼」
- 儀式が終わった後、「本日はありがとうございました」と言って、両手で渡す
お付き合いのある寺がない場合はどうする?
「お寺がわからない」「お寺が遠方で来てもらえない」という場合もあるでしょう。
その場合は、以下の方法があります。
方法1:近隣の同じ宗派のお寺に相談
自分の家の宗派がわかっていれば、近隣の同じ宗派のお寺に相談できます。
「お寺が遠方のため、閉眼供養をお願いできませんか?」と聞いてみましょう。
方法2:仏壇店や専門業者に「供養込みの処分」を依頼
仏壇店や仏壇処分の専門業者の中には、「供養込みの処分サービス」を提供しているところがあります。
業者が提携しているお寺の僧侶が供養を行ってくれます。
費用は3万円〜5万円程度が相場です。
ステップ3:仏壇の中身を整理する(位牌・仏具・掛け軸)
魂抜き供養が終わったら、仏壇の中身を整理します。
仏壇の中には、以下のようなものが入っています。
- 位牌(いはい):故人の名前が書かれた木の札
- 本尊(ほんぞん):仏像や掛け軸
- 仏具(ぶつぐ):りん、香炉、花立、ろうそく立てなど
- 経本(きょうほん):お経が書かれた本
- 過去帳(かこちょう):先祖の名前や命日が書かれた帳面
- 遺影・写真
それぞれの扱い方を見ていきましょう。
位牌の扱い方
位牌は、故人の魂が宿るとされる大切なものです。
魂抜き供養を行った後は、以下の方法で処分します。
方法1:お寺で合同供養(最も一般的)
- 費用:1万円〜3万円
- お寺に位牌を預け、他の家の位牌と一緒に供養塔に納めてもらう
- 最も一般的で、安心感のある方法
方法2:手元供養(ミニ位牌)に切り替える
- 費用:1万円〜3万円
- 小さな位牌を作り、老人ホームや自宅に置く
- 「これからも毎日手を合わせたい」という方に向いています
方法3:自分で処分
- 魂抜き供養を行った後であれば、自治体の可燃ゴミとして処分することも可能です
本尊・仏像・掛け軸の扱い方
本尊や仏像も、魂抜き供養を行った後は「ただの物」になります。
- お寺に引き取ってもらう(無料〜1万円)
- 仏具店に引き取ってもらう(無料〜5千円)
- 自治体の可燃ゴミとして処分(無料)
ただし、本尊は仏様の姿ですので、ゴミとして処分することに抵抗がある方も多いでしょう。
可能であれば、お寺や仏具店に引き取ってもらうのが無難です。
仏具(りん、香炉など)の扱い方
仏具は、以下の方法で処分できます。
- 金属製の仏具(りん、香炉など):自治体の不燃ゴミまたは資源ゴミとして処分
- 陶器製の仏具(花立、ろうそく立てなど):自治体の不燃ゴミとして処分
- 木製の仏具:自治体の可燃ゴミとして処分
経本・過去帳の扱い方
経本:
- 自治体の可燃ゴミとして処分または、お寺に引き取ってもらう
過去帳:
- 必ず保管しましょう
- 過去帳には、先祖の名前や命日が記録されており、家族の歴史が詰まっています
遺影・写真の扱い方
遺影:
- 自宅に飾る または、額縁は不燃ゴミとして処分可能
写真:
- 大切な写真は保管
- 不要な写真は、自治体の可燃ゴミとして処分
ステップ4:仏壇を処分する
最後に、仏壇本体を処分します。
仏壇の処分方法は、大きく分けて3つあります。
方法1:自分で自治体の粗大ゴミに出す
費用:1,000円〜2,000円
メリット:
- 費用が最も安い
デメリット:
- 自力で仏壇を屋外まで搬出する必要がある
- 大きな仏壇は、一人では運べない
- 階段がある場合、さらに困難
向いている人:
- 小さな仏壇(高さ100cm以下)
- 力のある家族や友人に手伝ってもらえる
方法2:仏壇店に依頼
費用:3万円〜8万円
メリット:
- 搬出から処分まで全て任せられる
- 日程調整がしやすい
デメリット:
- 費用が高い
向いている人:
- 大きな仏壇で自力搬出が無理
- 費用よりも手間を省きたい
方法3:仏壇の処分業者に依頼(推奨)
費用:2万円〜4万円
メリット:
- 供養もセットで対応してくれる
- 搬出から処分まで全て任せられる
デメリット:
- 費用が少しかかる
向いている人:
- 「仏壇を丁寧に扱ってほしい」という方
- 費用と安心感のバランスを重視する方
仏壇じまいにかかる費用相場とお布施の目安
「結局、全部でいくらかかるの?」
これが最も気になるポイントではないでしょうか。
仏壇じまいにかかる費用を、項目ごとに見ていきましょう。
費用の内訳
| 項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 魂抜き供養のお布施 | 1万円〜5万円 | 菩提寺との関係性や地域による。一般的には3万円前後。 |
| 位牌の処分・供養 | 1万円〜3万円 | 菩提寺での合同供養が一般的。 |
| 仏壇・仏具の処分費用 | 2万円〜10万円 | サイズや搬出の難易度による。専門業者なら3万円前後。 |
| その他(交通費など) | 0円〜1万円 | 僧侶が遠方から来る場合の交通費など。 |
| 合計 | 4万円〜20万円 | 平均的には8万円〜12万円 |
費用を抑えるポイント
ポイント1:仏壇・仏具は自分で処分する
仏壇や仏具は、自治体のゴミ回収を利用すれば無料で処分できます。
業者に依頼すると1〜3万円かかるので、自分で処分できるものは自分で処分しましょう。
自分で仏壇を処分する具体的な手順はこちらの記事でも詳しく解説しています。
→仏壇処分は自分でできる!お金も時間もかけずに進める5つの手順
ポイント2:複数の業者から見積もりを取る
仏壇店や処分業者に依頼する場合は、サービスによって料金が大きく異なります。
必ず3社以上から見積もりを取って比較しましょう。
まとめ|宗派や家族に合った方法で、後悔のない仏壇じまいをしよう
仏壇じまいは、決して「罰当たり」な行為ではありません。
正しい手順で、宗派に沿った方法で進めれば、ご先祖様に対しても、家族に対しても、誠実な供養となります。
まずは、家族や親戚に相談することから始めましょう。
家族の気持ちに寄り添いながら、一緒に最善の方法を考えることが、後悔のない仏壇じまいにつながります。
あなたの仏壇じまいが、安心して進められることを心から願っています。
【関連記事】