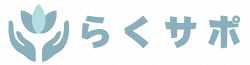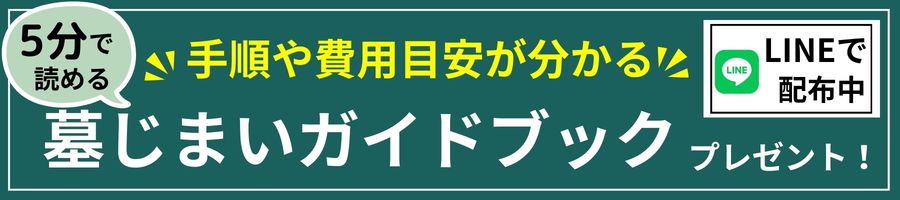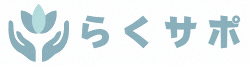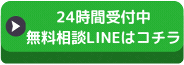墓じまいの永代供養が全てわかる!
手続き・費用・種類をやさしく解説
【2026年1月更新】
「永代供養って聞くけれど、具体的にどんなことをするの?」
「永代供養と墓じまいってどう違うの?」
そんな疑問を感じていませんか?
墓じまいを考えるとき、多くの方が次に悩むのが「お骨の行き先」です。
その選択肢として注目されているのが、お寺や霊園が遺骨を永く供養してくれる“永代供養”です。
しかし、「費用はいくらかかるのか」「どんな種類があるのか」「どこに依頼すればいいのか」など、
初めてだとわからないことばかり。
この記事では、墓じまい後の永代供養の意味・流れ・費用相場・選び方まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
読み終えるころには、
「自分の家にはどんな永代供養が合っているか」
「どのように手続きすればいいか」
が明確になり、安心して次の一歩を踏み出せるようになります。
Check
この記事を読んで理解できること
- 永代供養の種類と特徴比較
- かかる費用相場と安い永代供養
- 永代供養の申込の流れ
目次
そもそも「永代供養」とは?
永代供養とは、お墓の管理や供養をお寺や霊園が代わりに行ってくれる供養方法のことです。
通常は子どもや親族がお墓を継ぎ、法要や清掃を続けていきますが、
永代供養では、その役割を寺院や霊園が引き継いでくれます。
契約の際に「永代供養料」と呼ばれる費用を一括で支払うことで、
定期的な供養や管理を永続的に行ってもらえるのが特徴です。
多くの寺院では年に数回、合同法要などを開催しており、
遺族が参加できない場合でも安心して故人を弔うことができます。
少子化・墓守の不在により永代供養は増えている
近年、永代供養を選ぶ人が増えている背景には、社会的な変化があります。
永代供養を選ぶ理由
- 子どもが遠方に住んでおり、お墓を守れない
- 継承者がいない、または単身世帯が増えている
- お墓の維持費や草取りなどの管理負担を減らしたい
このような理由から、「自分の代でお墓をしまう(墓じまい)」+「永代供養で供養を託す」という選択が増えています。
特に、都市部ではお墓を継ぐ文化が薄れ、
「お寺に任せて安心したい」「子どもに負担をかけたくない」という考え方が主流になりつつあります。
永代供養と通常のお墓の違い
通常のお墓(先祖代々墓)は、家単位で代々引き継ぎ、家族が供養や管理を行うのが一般的です。
一方で永代供養は、お墓の管理・供養を第三者(寺院・霊園)が代行する点が大きな違いです。
通常のお墓と永代供養の違い
| 通常のお墓 | 永代供養 | |
|---|---|---|
| 管理者 | 家族・子孫 | 寺院・霊園 |
| 供養の方法 | お墓ごとに供養 | 個別供養または合同供養 |
| 費用 | 維持費を毎年支払う | 一回払うと維持費無し |
| お墓の継承 | 必要 | 不要 |
| お墓の形 | 墓石 | 納骨堂・樹木葬など |
「家族に負担をかけずに供養を続けたい」「墓じまいを機にスッキリ整理したい」
という方にとって、永代供養は負担なく安心できる供養の形といえます。
墓じまいと永代供養の違い
「墓じまい」と「永代供養」は似ている言葉ですが、実際には目的と役割が異なるものです。
墓じまいは、今あるお墓を撤去し、更地に戻す「整理の手続き」です。
これに対して、永代供養は、撤去したお墓から取り出した遺骨を「新しい供養の形」で預けることを指します。
墓じまいと永代供養の違い
墓じまい=“お墓を撤去して閉じる”こと
永代供養は“墓じまい後の供養方法”のこと
多くの方は、この2つをセットで行うことで、
「お墓を管理する人がいなくても安心して供養を続けられる形」に整えています。
このように、
- 墓じまい=過去を整理するステップ
- 永代供養=未来に供養をつなぐ仕組み
と考えると、両者の関係が分かりやすくなります。
永代供養したお骨はどうなる?
墓じまいで取り出したお骨は、永代供養墓や納骨堂に移され、寺院や霊園によって長期間、もしくは永続的に供養・管理されます。
納骨の方法にはいくつかの形があります。
- 個別供養型:専用の納骨スペースに安置し、一定期間は個別で管理
- 合同供養型:他の方の遺骨と一緒に埋葬し、合同法要で供養
- 納骨堂・樹木葬型:屋内施設や自然の中で供養
多くの寺院では、最初の数年間は個別供養 → その後は合同供養へ移行という形をとっています。
永代供養は、一定期間は個別埋葬のため遺族は参拝でき、数年後は他のお骨と一緒に埋葬される仕組みです。
お骨は、寺院の敷地内や霊園の合同供養塔などに納められ、年に数回の法要の際に僧侶による読経が行われます。
このように永代供養は、「お墓を持たずに供養を続ける」ための選択肢であり、墓じまいを行った後の自然で安心できる供養のかたちとして広がっています。
永代供養の種類と特徴を比較
永代供養と一口に言っても、その形はさまざまです。
お寺の境内にある「永代供養墓」から、屋内型の「納骨堂」、自然と一体化した「樹木葬」まで、
ライフスタイルや希望に合わせて選べるようになっています。
ここでは代表的な4つのタイプを紹介し、それぞれの特徴と向いている人の傾向を解説します。
永代供養の種類
- 個別供養墓
- 合同供養墓(合祀墓)
- 納骨堂
- 樹木葬
個別供養墓
個別に骨壺を納めるタイプで、一定期間(例:13年・33年など)は他の方と分けて安置されます。
期間が過ぎた後は、合同供養墓に移されることが一般的です。
特徴
- 契約期間中は個別でお参りできる
- 一定期間後に合祀される(永代的に供養)
- 永代供養の中でも比較的高額(20〜50万円前後)
こんな人におすすめ
- 今までのお墓と同様、個別に供養したい
- 一定期間は自分たちでお参りしたい
- お寺との関係を保ちながらお墓を整理したい
合同供養墓(合祀墓)
複数の遺骨をひとつの墓所にまとめて納める形式です。
お骨は他の方と一緒に埋葬されるため、個別の参拝はできません。
特徴
- 永久的に寺院や霊園が供養・管理してくれる
- 個別の墓石が不要で、費用が最も安い(5〜15万円程度)
- 継承や管理の心配がいらない
こんな人におすすめ
- 継ぐ人がいない、単身世帯の方
- 費用をできるだけ抑えたい
- 「供養をきちんと続けたい」気持ちはあるが、管理の負担を減らしたい
納骨堂(屋内型)
建物の中に遺骨を安置するタイプで、屋内でお参りできるのが特徴です。
近年は、都市部を中心に急速に増えています。
特徴
- 屋内で天候に左右されずお参りできる
- 宗派を問わず利用できる施設が多い
- 一部の施設ではカード式や自動搬送型システムを導入
- 費用は30〜80万円程度(立地により変動)
こんな人におすすめ
- 駅近・アクセス重視で選びたい
- 継承者がいなくても安心して利用したい
- バリアフリー設計の屋内でお参りしたい
樹木葬
墓石を建てず、樹木や花を墓標とする自然葬の一種です。
お墓というよりも「自然に還る」ことを重視した新しい供養の形として人気が高まっています。
特徴
- 自然環境の中で供養できる
- 管理費が不要または低額(10〜40万円程度)
- 宗派・宗教を問わない施設が多い
- 合同型・個別型の両方がある
こんな人におすすめ
- 自然の中で眠りたい
- 宗教にとらわれず自由な供養が良い
- 墓石を建てず、管理費のかからない形を選びたい
永代供養墓を選ぶ際のチェックポイント
永代供養を選ぶ際は、「費用」や「宗派」だけでなく、
「個別埋葬を重視するか」や「アクセスの良さ」も確認しておくことが大切です。
チェックしておくべき主なポイントは次の通りです。
- 供養の方法:個別か合同か、何年後に合祀されるか
- 立地・アクセス:家から通える距離か、交通手段は確保できるか
- 宗派・管理体制:自分の宗派で利用できるか、寺院が直接管理しているか
- 費用の内訳:永代供養料のほか、管理費や年会費が必要か
- 契約内容:契約期間・更新の有無・解約時の扱いなど
この5つを確認しておくことで、後々のトラブルや不安を避けられます。
永代供養は「安いから」「同じお寺だから」といった理由だけで決めるのではなく、
ご家族の方針やお参りのアクセスなどを基準に選ぶことが大切です。
永代供養の費用相場と内訳
永代供養は「お墓の維持費がかからない」と言われますが、実際には初期費用や供養の仕方によって金額に大きな幅があります。
ここでは、全国的な平均相場と費用の内訳、そして契約時に注意すべきポイントを解説します。
永代供養料の全国平均は10〜50万円が目安
全国的に見ると、永代供養の費用は 10万〜50万円前後が相場です。
ただし、供養の形式や納骨の方法によって金額は変わります。
| 供養の種類 | 費用相場 | 特徴 |
|---|---|---|
| 合同供養墓(合祀) | 5〜15万円 | 他の方と一緒に埋葬される。最も安価で維持費不要。 |
| 個別供養墓 | 20〜50万円 | 一定期間(例:13年)個別で安置。期間終了後は合祀へ。 |
| 納骨堂 | 30〜80万円 | 屋内施設型。立地や設備により費用差が大きい。 |
| 樹木葬 | 10〜40万円 | 自然葬タイプ。墓石を建てず管理費が安い。 |
永代供養は、それぞれ費用に差はありますが、
一般的なお墓の建設費(平均100万円以上)に比べると負担が軽く、維持管理も不要なため、
「墓じまい後の負担を減らしたい方」に選ばれています。
初期費用と管理費の違い
永代供養には大きく分けて、初期費用と管理費の2種類の費用があります。
永代供養の費用
・初期費用(永代供養料)
契約時に一括で支払う費用で、供養や管理を永続的に行うための基本料金です。
一般的には「供養料」「納骨料」「管理料」などが含まれています。
多くのケースが一括精算で、この費用を支払えば、その後の維持費が不要な場合が多いです。
・管理費(年会費) *年間管理費不要な場所も有り
一部の納骨堂や寺院では、施設維持や清掃のために年間5,000円〜1万円程度の管理費を徴収しているところもあります。
永代供養といっても「永続的=追加費用なし」とは限らないため、契約前に確認が必要です。
契約内容によって変わる費用の注意点
永代供養の費用は、「契約内容」と「期間設定」によって変わる場合があります。
主な注意点は次の3つです。
- 期間付きか、永年かを確認する
- 「永代供養」と名がついていても、実際には13年・33年などの契約期間つきである場合があります。
*契約期間後は合祀されるのが一般的です。
- 「永代供養」と名がついていても、実際には13年・33年などの契約期間つきである場合があります。
- 法要や納骨式の費用が別料金のこともある
- 契約時の費用に含まれない場合、 開眼供養や納骨法要の際に別途1〜3万円程度のお布施が必要になることがあります。
- 改葬費用(墓じまい費用)は別途必要
- 永代供養の契約には、お墓の撤去や遺骨の移動費用は含まれていません。
墓じまいを行う場合は、別途10万〜30万円前後の撤去費用がかかる点にも注意しましょう。
- 永代供養の契約には、お墓の撤去や遺骨の移動費用は含まれていません。
永代供養は「費用が安くて管理がラク」というメリットがある一方で、
契約内容によっては追加費用が発生することもあります。
金額の安さだけで決めず、「何が含まれていて、何が別料金なのか」を明確にしてから契約することが大切です
墓じまいから永代供養までの手続きの流れ
永代供養を行うには、まず「墓じまい」をして、今あるお墓から遺骨を取り出す必要があります。
手続きには行政の許可が必要で、寺院や霊園とのやり取りも発生するため、
流れを正しく理解しておくことがスムーズな進行のポイントです。
ここでは、改葬許可証の申請から永代供養墓への納骨までの手順を分かりやすく解説します。
① 改葬許可証の申請(行政手続き)
墓じまいをして遺骨を他の場所へ移す際には、「改葬許可証」の取得が必要です。
これは、現在の墓地がある市区町村の役所に申請します。
主な流れは以下の通りです。
- 改葬許可申請書の入手(市役所の窓口かホームページで入手)
- 現在の墓地の管理者(寺院や霊園)から「埋葬証明書」または「使用許可証」をもらう
- 新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂など)から「受入証明書」をもらう
- 上記の2つを添付して役所に提出 → 「改葬許可証」が発行される
改葬許可証は、遺骨を新しい供養先へ移動させるために必要な書類であり、
これがないと納骨堂や永代供養墓に受け入れてもらえない場合があります。
② 永代供養墓の申し込み手順
改葬許可証を取得したら、次に永代供養先の寺院や霊園に申し込みを行います。
申し込み時の一般的な流れは次の通りです。
- 永代供養墓の種類・契約プランを選ぶ(個別・合同・納骨堂など)
- 契約書の内容(供養期間・合祀時期・費用)を確認
- 契約金・永代供養料を支払う
- 納骨式や法要の日程を調整
寺院によっては、「納骨式の際に僧侶による読経(開眼供養)」を行うこともあります。
この場合は、別途お布施(1〜3万円程度)が必要になることがあります。
③ お墓じまいをする
改葬許可証の申請、永代供養墓の申込みが完了したら、お墓じまいをします。
主な流れは次の3ステップです。
- 閉眼供養(魂抜き)を行う 僧侶に読経をお願いし、お墓の魂を抜く儀式を行います。 お布施は一般的に2〜5万円ほどです。
- 遺骨を取り出し、保管する 石材業者が墓石を一時的に解体し、遺骨を取り出します。 改葬許可証を添えて丁寧に保管しておきましょう。
- 墓石の撤去・更地化 墓石を撤去し、更地に戻してお墓の管理者へ返還します。 費用は1㎡あたり3〜5万円前後が目安です。
作業が終わったら、遺骨を新しい納骨先(永代供養墓など)へ移動させ、
改葬許可証を提出して納骨手続きを完了します。
お墓じまいは、閉眼供養から撤去まで1〜2日で終わることが多いですが、
事前に寺院や霊園の了承を得て進めることが大切です。
お墓じまいの手順については、こちらの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
→墓じまいの手続きはこれでOK|やるべき順番を最初から最後まで解説
手続きの期間と注意点
墓じまいから永代供養までの全体期間は、おおよそ1〜2ヶ月程度が目安です。
ただし、寺院や霊園との日程調整や行政の審査に時間がかかる場合もあります。
進める際の注意点は以下の通りです。
注意点
- 必ずお墓の管理者の了承を得てから手続きを始める
- 無断で進めるとトラブルの原因になります
- 改葬許可証の有効期限を確認する
- 通常は3ヶ月以内です。期間内に完了させましょう。
- 複数の遺骨がある場合は、人数分の改葬許可証が必要
- 契約書はコピーを保管し、後のトラブルに備える
また、遠方で手続きが難しい場合は、家族や業者への委任も可能です。
市役所に「委任状」を提出すれば、代理人が改葬許可証を申請することができます。
墓じまいから永代供養までの流れを整理しておけば、
手続きに迷うことなく、安心して新しい供養先へと移行できます。
焦らず、一つずつ確実に進めることが大切です。
永代供養先の選び方と相談先
永代供養を安心して任せるには、「どこに依頼するか」を見極めることが大切です。
永代供養先には大きく分けて 寺院・公営霊園・民間霊園 の3つがあり、特徴や費用、管理体制が異なります。
寺院・公営霊園・民間霊園の特徴比較
| 種別 | 特徴 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 寺院 | 僧侶が、読経や法要を定期的に実施 | 供養が手厚く安心感がある | 宗派が限定される場合がある |
| 公営霊園 | 自治体が運営、霊園スタッフが管理 | 費用が安く、宗派を問わない | 抽選制・募集期間が限られる |
| 民間霊園 | 民間事業者が運営 | 交通アクセスが良く、デザインや設備が豊富 | 費用や契約内容に差が大きい |
選ぶポイント
永代供養先は、以下の通り選ぶのがオススメです
「費用を抑えたい」 →公営霊園
「宗派にこだわりたい」 →寺院墓地
「利便性やデザインを重視したい」 →民間霊園
できる限り見学して選ぼう
永代供養墓は、パンフレットや写真だけではわからない点も多いため、できる限り現地を見て確認しましょう。
特に注目したいのは次の3点です。
- 供養や管理が行き届いているか
- 実際に供養が定期的に行われているか、清掃・管理が行き届いているかを確認。
- 立地とアクセス
- 将来、家族が訪れやすい場所かどうかも大切な判断基準です。
- 契約内容の明確さ
- 合祀(ほかの遺骨と一緒にする)になる時期や、供養期間、費用の内訳を必ず確認しましょう。
「永代供養料に含まれる内容(供養・管理・法要)」を明記している霊園は信頼性が高い傾向にあります。
まとめ|自分に合った永代供養を見つけてみよう
墓じまいを終えたあとの永代供養は、これからの供養をどう続けていくかを決める大切なステップです。
永代供養と一口に言っても、個別供養・合同供養・納骨堂・樹木葬など、形も費用もさまざまです。
大切なのは、「誰が供養を続けるのか」「どんな形で弔いたいのか」という自分たちの思いに合った方法を選ぶこと。
メリットはそれぞれですが、最終的には「安心して託せる場所」であることが何より重要です。
まずは、気になる永代供養先の資料を取り寄せたり、現地を見学したりしてみましょう。
一歩踏み出すことで、「これなら安心できる」という納得の供養の形がきっと見つかります。