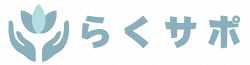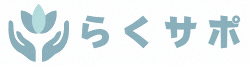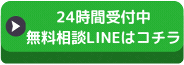仏壇処分は自分でできる!
お金も時間もかけずに進める5つの手順
【2026年3月更新】
「仏壇って、自分で処分してもいいの?」
「お坊さんを呼ばなきゃダメ?でもそんな余裕もないし…」
仏壇を整理しようと思っても、どうすればいいのか分からずに困っていませんか?
特に、お付き合いのあるお寺がなかったり、仏壇店が近くにない方は、
「結局、自分でやるしかない…」と悩んでしまう方も多いはず。
この記事では、費用をかけず、でも最低限のマナーは守りながら、
仏壇を自分の手で安心して処分するための5つのステップをわかりやすくご紹介します。
急ぎの方でもすぐに動けるよう、今日からできる実践的な方法も解説しています。
「きちんと片付けたい」「でも、難しいことは避けたい」そんなあなたのための記事です。
Check
この記事を読んで理解できること
- 仏壇を自分で処分する5つのステップ
- 自分で処分するときの注意点とマナー
- 最低限守りたい「お清め」のポイント
処分にお困りの
仏壇お引取りします
搬出から積込みまで全て対応
お仏壇の供養も対応
お仏壇の処分8,000円から
年中無休・24時間受付中
タップしてお電話ください
目次
実は多くの人が「仏壇を自分で処分」している
近年、ライフスタイルの変化や核家族化、お寺への関わり方の変化もあり、仏壇の処分を「自分で行う」選択をする人は増えています。
実家の整理や空き家の片付けに際して、
「仏壇を引き継ぐ人がいない」「新居に置くスペースがない」といった事情もあり、
供養や感謝の気持ちを込めながら、自力で片付けるというのが現代の一つの流れになりつつあるのです。
もちろん、不安な気持ちがあるのは自然なこと。
ですが、「正しい手順」や「最低限のマナー」を知れば、心残りなく処分することができます。
この記事では、そのためのステップを丁寧に解説していきます。
「自分でやってもいいんだ」と安心して進められるよう、一緒に見ていきましょう。
お金も時間もかけない!
仏壇処分の5つのステップ
仏壇を自分で処分することは、決して特別なことではありません。
ここでは、費用も時間も最小限に抑えながら、「気持ち」と「マナー」だけは大切にするための5つのステップをご紹介します。
自宅でできることばかりなので、以下の手順に従って進めましょう。
ステップ1:仏壇の中身を整理する(位牌・遺影・仏具の扱い)
まず最初に行うのは、仏壇の中にあるものの仕分けです。
- 位牌(いはい)
- 遺影(写真)
- 数珠やおりんなどの仏具
- お供え物やお花
- 引き出しの中の貴重品(通帳やハンコなど)
これらはすぐに捨てるのではなく、「ありがとう」「おつかれさまでした」と声をかけて整理していきましょう。
仏具や位牌は、後述の「簡易供養」でまとめて供養するか、気になる場合は郵送供養や地域のお寺に引き取りを相談してもOKです。
ステップ2:供養やお清めを行う(自宅でできる範囲でOK)
次に行うのが、「仏壇の供養」です。
本来であれば、お坊さんを呼んで供養のお経をあげてもらうのが一般的ですが、
どうしてもお坊さんを呼べない場合は、以下の手順で供養をしましょう。
- 仏壇の前で手を合わせる
- お線香やロウソクを灯す
- お清めの塩をふる(仏壇の四隅や中に少量でOK)
- 感謝の気持ちを書いた紙を添える
形式にとらわれず、自分なりのやり方で「ありがとう」とお別れの気持ちを伝えることが大切です。
これだけでも、心が少し軽くなり、「ちゃんと区切りがつけられた」と感じられる人も多くいます。
ステップ3:仏壇を解体・分別する(素材別に分ける)
供養が済んだら、いよいよ仏壇本体の処分準備です。
処分の方法は、「粗大ごみに出す」か「一般ごみに出す」方法があります。
粗大ごみの場合は、そのままの状態で出すことができますが、一般ごみの場合は、解体・分別して出す必要があります。
【分別の例】
- 木材部分 → 粗大ごみ・可燃ごみ(小型に分解)
- ガラス扉 → 不燃ごみ・危険物
- 金具・ネジ → 小型金属や不燃ごみ
※背が高く大型な仏壇は、無理に解体せず「粗大ごみ」で出しましょう。
ステップ4:自治体の粗大ごみや一般ごみとして処分する
お仏壇の整理や供養が完了したら粗大ゴミなどで処分できます。
以下のとおり処分しましょう
- 解体前の仏壇→ 粗大ごみ
- 小型に解体した木材 → 可燃ごみ
- ガラスや金具 → 不燃ごみ
粗大ごみは、自治体の予約制になっていることが多いため、「〇〇市 粗大ごみ 予約」で検索し、ネットまたは電話で申し込みましょう。
粗大ごみに出す時は以下を参考ください:
- 料金:1000円〜2000円程度
- シールを購入して貼り付け
- 指定日に家の前に出すだけ
外部業者を使うよりも、処分費用が抑えられます。
ステップ5:残った不安や気持ちに「自分なりの区切り」をつける
物理的な処分が終わった後、ふと「これでよかったのかな?」と不安になることもあります。
そんなときこそ、自分の気持ちにそっと寄り添う時間を取ってください。
- 写真だけ残して思い出を形にする
- 手紙を書いて供養したことを記録に残す
- 家族に「ちゃんとやったよ」と報告する
このステップは、仏壇処分の「最後の仕上げ」です。
形式ではなく「自分なりのけじめ」をつけることで、心の中でもすっきりとお別れできるはずです。
仏壇処分を自分で行うときの注意点とマナー
仏壇は家具とは違い、ご先祖様の魂を祀る大切な存在です。
そのため、処分の際にも「粗末にしない」「感謝の気持ちを忘れない」という心構えがとても大切です。
ここでは、仏壇を自分で処分する場合に注意したいマナーや、最低限の供養の考え方についてご紹介します。
自分で処分する時に注意したいマナー
一般的に、仏壇を処分する前には「魂抜き(閉眼供養)」という儀式を行うのが望ましいとされています。
これは、ご先祖様の魂やご本尊を仏壇からお戻しし、「今までありがとうございました」と感謝を伝えるための供養です。
本来であれば、お付き合いのあるお寺にお願いしてお経をあげてもらうのが正式な手順ですが、
現在では以下のような理由で、難しい方も多くなっています:
- 菩提寺が遠方にある、あるいは関係が途絶えている
- そもそもお寺との付き合いがない
- お布施の金額が分からず不安
- 急ぎで対応が必要な状況
このような事情から、「正式な魂抜きは難しいが、気持ちだけは大切にしたい」と考える方も多く、
自宅で簡単な供養をされる方もいらっしゃいます。
こうした場合は、「丁寧に扱い、感謝の気持ちで送り出す」という姿勢をマナーとして持っておきましょう。
最低限守りたい「お清め」のポイント
自宅で供養をする場合でも、次のような簡単なお清めの手順を取り入れることで、心を込めたお別れができます。
自宅でできるお清めの例:
- 仏壇の前で静かに手を合わせる(できれば家族も一緒に)
- お線香やロウソクを灯して祈る
- 仏壇の四隅や中に、お清めの塩を少量ふる(粗塩がおすすめ)
- 「今までありがとうございました」と声に出して伝える
- 仏壇をきれいに拭いてから処分する
これらは宗派による厳密なルールではなく、心を込めて送り出すための“区切り”の儀式です。
「これで大丈夫かな…」と迷ったときは、
「ご先祖様に対して失礼のないように、誠実な気持ちで対応できたかどうか」を、自分なりの判断基準にするとよいでしょう。
不安が残る時は供養サービスを利用してみよう
「気持ちを込めて自分で処分するつもりだけど、本当にこれでよかったのか心配…」
「仏壇は処分できたけど、魂抜きをしていないのが気にかかる」
そうした不安を感じる方も多いものです。
無理に一人で抱え込まず、費用を抑えつつ供養や処分を手伝ってくれる外部サービスをうまく活用するのも一つの方法です。
ここでは、安心感とコストのバランスが取れた選択肢をご紹介します。
お坊さんに来てもらわず供養だけお願いするサービス
「閉眼供養(魂抜き)だけはきちんとしたいけど、場所が遠くてお坊さんに来てもらえない」
そんなときは、郵送で供養を依頼できるサービスが便利です。
位牌を郵送するだけで供養をしてもらえるので、時間に余裕を持って供養を依頼することができます。
利用方法:位牌を郵送
料金相場:5000円〜8000円
「お坊さんを呼ばなくても、ちゃんと気持ちは届けたい」という方におすすめです。
仏壇が大きくて処分できない場合は専門業者に相談しよう
仏壇の運び出しや処分がどうしても難しい場合は、供養付きで引き取りまでしてくれる専門業者を利用するのも有効です。
以下のような方に向いています:
- 高さが140cm以上の大型仏壇で、自力で運び出せない
- 車がなく、自治体の粗大ごみ回収にも出せない
- 仏具や位牌もまとめて処分したい
相場感:
- 小型仏壇:10,000〜15,000円程度
- 大型仏壇:20,000〜50,000円程度
- お布施料:20,000円〜30,000円程度
仏壇のサイズや搬出のしやすさによって費用は変わるため、複数社に見積もりを取るのが安心です。
まとめ:自分でできるからこそ、気持ちを込めて処分しよう
仏壇の処分は、「ただの家具」とは違い、ご先祖様や家族との思い出が詰まった大切な存在とのお別れでもあります。
だからこそ、「失礼のないように」「きちんとやりたい」という気持ちが湧くのは、ごく自然なことです。
本記事では、自分の手で仏壇を処分する方法や、その際に気をつけたい供養のマナー、そして不安を和らげる外部サービスの選択肢までをお伝えしてきました。
正式な儀式や立派な方法でなくても、「ありがとう」「おつかれさまでした」という気持ちを込めて向き合えば、それは立派な供養のかたちになります。
この記事が、あなたの「後悔のない仏壇処分」のきっかけになることを祈っております。