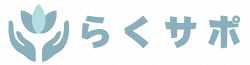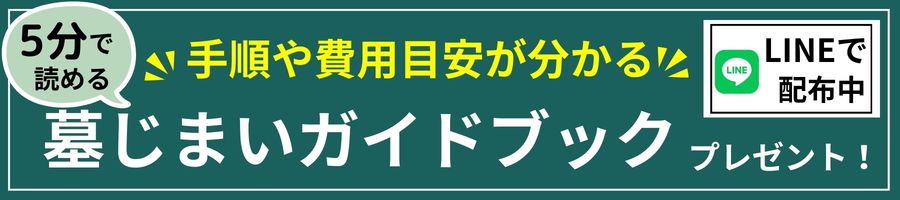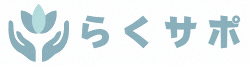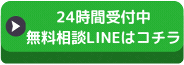お金がなくても大丈夫!
墓じまい補助金の全情報と安く進めるコツ
【2026年1月更新】
「墓じまいをしたいけれど、費用の負担が心配…。」
そんなときに役立つのが「墓じまいの補助金制度」です。
自治体によっては、お墓の撤去や改葬にかかる費用の一部を補助してくれる制度があります。
この記事では、補助金の概要から、自分の地域での調べ方、申請方法、そして補助金がない場合の費用を抑えるコツまで、わかりやすく解説します。
読み終えるころには、
「自分の地域で補助金が使えるのか」
「使えない場合にどう進めるか」
が明確になり、安心してお墓じまいが進めるようになります。
Check
この記事を読んで理解できること
- 墓じまい補助金が使える自治体の情報
- 自分の地域で補助金があるか調べる方法
- 補助金がない時に費用を抑える方法
目次
墓じまいの補助金とは?制度の目的
墓じまいの補助金とは、お墓を撤去・整理する際に自治体が費用の一部を支援してくれる制度のことです。
主に、高齢化や後継者不足で「お墓を管理できない世帯」を支援する目的で設けられています。
なぜ補助金制度があるのか
一般的に、墓じまいの費用は20万円〜50万円前後が相場です。
内訳は、墓石の撤去・処分費用、遺骨の取り出し、整地作業など。
この金額は決して小さくなく、特に年金生活の方や遠方の親族にとっては大きな負担になります。
そのため、自治体によっては「経済的負担を軽減し、放置された墓(無縁墓)を防ぐ」という目的で、
墓じまい費用の一部を補助金として支給しています。
たとえば、3万円〜10万円の範囲で支給する自治体が多く、
撤去業者への支払い後に申請すれば、後日口座に還付されるケースもあります。
自治体が制度を設ける背景(無縁墓防止・墓地整理)
近年、お墓の管理者がいなくなる「無縁墓(むえんぼ)」が社会問題となっています。
お墓を放置すると、雑草が生い茂ったり、墓石が倒壊したりして景観や安全面の問題が発生します。
そこで多くの自治体では、
- 管理が難しい墓地の整理を促進する
- 将来的な墓地の維持管理コストを抑える
- 墓地を有効活用し、共同墓地や永代供養墓へ転換しやすくする
といった目的で「墓じまい補助金制度」を設けています。
つまり、この制度は個人の経済的支援だけでなく、地域全体の墓地管理を持続可能にするための取り組みでもあるのです。
補助金がもらえる自治体は全国的にも少ない
墓じまいに対して補助金や助成制度を設けている自治体は全国でも少数です。
また、制度を利用できるお墓は基本的に「市営墓地・公営墓地」が対象のため、
ほとんどの市区町村のお墓で、墓じまい補助金制度は利用できません。
ただし、一部の自治体では補助金制度を設けています。
以下に代表的な自治体の実例と内容を紹介します。
墓じまい補助金制度がある自治体
自分の地域で補助金があるか確認する方法
墓じまいの補助金は、全国一律の制度ではなく、市区町村の自治体の制度です。
そのため、まずは自分の住んでいる市区町村、もしくはお墓がある地域で補助金制度があるかを確認することが第一歩になります。
1.市町村公式サイトで検索
最も手軽なのは、各自治体の公式サイトで検索する方法です。
検索窓に次のようなキーワードを入れて探してみましょう。
- 「〇〇市 墓じまい 補助金」
たとえば「岐阜市 墓じまい 補助金」と検索すると、岐阜市の公式サイトに掲載された「墓所返還補助制度」の案内ページが見つかります。
このように、自治体ごとに制度名や呼び方が少し異なるため、「墓じまい」だけでなく「改葬」「墓地返還」などの関連語でも調べるのがコツです。
2.役所に問い合わせる
制度が見つからなかった場合は、役所に直接問い合わせてみましょう。
電話で「墓じまいの補助金や助成制度について教えてください」と伝えれば、担当課へつないでもらえます。
自治体によっては、改葬や墓地管理を担当する部署が明記されていない場合もあるため、まずは代表電話で確認するとスムーズです。
補助金の申請方法と必要書類
墓じまいの補助金を受け取るためには、自治体ごとの申請ルールに沿って、必要書類を揃えて提出する必要があります。
ここでは、一般的な申請の流れと必要書類、申請時の注意点をわかりやすく解説します。
一般的な申請の流れ
補助金の申請は、どの自治体でもおおむね次のような流れで進みます。
| 1.補助金交付申請書の提出 | まずは自治体の窓口や公式サイトから「墓地返還・改葬補助金申請書」などの様式を入手し、必要事項を記入します。 |
| 2.工事見積書の提出 | 墓じまいを依頼する業者の見積書を添付します。 |
| 3.工事完了後の領収書提出 | 工事が終わったあと、支払証明として業者の領収書を提出します。 |
| 4.改葬許可証や証明書の提出 | お墓の返還や改葬が正式に完了したことを示す書類(改葬許可証・受入証明書など)を添付します。 |
| 5.自治体による審査・振込 | 提出された書類が審査され、問題がなければ後日、指定口座に補助金が振り込まれます。 |
自治体によって、申請の順番(事前・事後)や書類の呼び方が多少異なることがあります。必ず事前に役所へ確認しましょう。
申請のタイミングと注意点
補助金の申請タイミングは自治体によって「工事前」と「工事後」のどちらかで異なります。
- 工事前申請タイプ: 申請書と見積書を先に提出し、審査・承認を受けた後で工事を行う。
- 工事後申請タイプ: 工事が終わった後に領収書や写真を提出して申請する。
どちらの方式でも共通して重要なのは、工事前に自治体へ確認しておくことです。
補助金対象外の工事を先に行ってしまうと、あとから申請しても受理されないケースがあります。
また、申請期限が「年度内(例:3月末まで)」と決まっている自治体も多いため、スケジュールには十分注意しましょう。
補助金がない地域で費用を抑える方法
残念ながら、墓じまいの補助金制度はすべての自治体にあるわけではありません。
しかし、補助金がなくても工夫次第で総費用を数万円単位で抑える方法があります。
ここでは、実際に多くの方が実践している3つの節約方法を紹介します。
業者の相見積もりを取る(費用比較で3〜5万円削減)
墓じまい費用を抑える最も効果的な方法は、複数の業者から見積もりを取ることです。
同じ規模・同じ作業内容でも、業者によって見積額に大きな差が出ることがあります。
たとえば、同じ1坪のお墓の墓石撤去で、
- A社:32万円
- B社:29万円
- C社:27万円
というように、3〜5万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
最近では、電話やLINEで現地写真を送るだけで見積もりを取れる業者も増えています。
最低でも2〜3社に依頼し、条件を確認した上で、納得できる業者を選びましょう。
合同供養墓・海洋散骨など費用が安い供養方法を選ぶ
墓じまい費用の中で大きな割合を占めるのが、新しい納骨先の費用(改葬先)です。
この部分を見直すことで、総額を大幅に減らせます。
たとえば、個別墓に建て替える場合は数十万円以上かかりますが、
- 合同供養墓:10〜15万円程度
- 海洋散骨:3万円程度
最近では、寺院や公営霊園が「永代供養付きの合同墓」を提供しており、
お墓の管理費がかからないため、将来的な維持費も不要になります。
「跡継ぎがいない」「将来の負担を減らしたい」と考えている方には、
費用と安心のバランスが取れた選択肢です。
親族で作業を分担して費用を節約する方法
墓じまいには、石材店や業者への依頼以外にも、自分たちでできる作業があります。
それらを家族で分担することで、費用を抑えられます。
たとえば、
- 行政の手続きを自分で行う
- 僧侶による供養の手配を自分で行う
- 改葬先の契約を直接申し込む
これらの作業を業者にすべて任せると、1〜3万円ほど上乗せされることがあります。
家族で協力してできる範囲を決めておくことで、結果的に数万円の節約につながります。
費用を抑えるポイント
補助金がない地域でも、
- 複数見積もりの比較
- 改葬先の見直し
- 自分でできる部分の対応
この3つを意識するだけで、無理のない費用で墓じまいを進めることができます。
補助金以外に、お金がない場合に使えるポイント
「墓じまいをしたいけれど、お金の余裕がない…」
そんな理由で手続きを先延ばしにしている方も少なくありません。
しかし、実際には費用を抑えながら、無理なく墓じまいを進める方法があります。
ここでは、補助金以外の支援策や、分割払いなどの現実的な選択肢を紹介します。
分割払いや後払いに対応している業者もある
近年では、墓じまいの需要増加に伴い、支払い方法の柔軟な業者が増えています。
特に「分割払い」や「後払い」に対応している業者を選べば、まとまった資金がなくても着手できます。
たとえば、総額30万円の墓じまい費用を
- 複数回払いにできるローン(メモリアルローン)
- 作業完了後の後払い
- クレジットカード払いやPayPay決済
などに設定できるケースがあります。
ただし、契約前に必ず「分割手数料の有無」や「支払いスケジュール」を確認しておきましょう。
無理のない範囲で計画的に進めるポイント
お墓の整理は「今すぐすべて終わらせなければならない」ものではありません。
費用面で不安がある場合は、段階的に進める計画を立てるのも一つの方法です。
たとえば、次のように進めると負担を分散できます。
- まずは役所で改葬手続きの流れを確認(無料)
- 見積もりを取り、費用感を把握
- 分割・後払いなど支払い方法を相談
- 無理のない時期に施工を依頼
このように順序立てて動くことで、焦らず・確実に・費用を抑えて墓じまいを進めることが可能です。
「お金がないから」と諦める必要はありません。
支援制度や柔軟な支払いプランをうまく活用すれば、今の状況に合わせた形で墓じまいを行うことができます。
まとめ|補助金がなくても、工夫次第で墓じまいは進められる
墓じまいの補助金制度は全国的に見るとまだ限られており、すべての自治体で利用できるわけではありません。
しかし、補助金がないからといって「墓じまいを諦める」必要はありません。
実際には、相見積もりの活用・改葬先の見直し・後払いの相談など、負担を軽くする方法はいくつもあります。
中には、ローンやカード払いに対応している業者もあり、まとまった資金がなくても着手できるケースもあります。
また、社会福祉協議会の「生活福祉資金貸付制度」や、寺院による「供養費の減免制度」など、
公的・民間の支援を相談できる窓口もあります。
大切なのは、焦らず一歩ずつ計画を立てることです。
まずは役所や墓じまい業者に相談し、費用や流れを具体的に把握してみましょう。
補助金がなくても、あなたに合った方法で無理なく進めることができます。
少しずつ準備を整えながら、安心できる形でご先祖のお墓を整えていきましょう。